研修医より
研修1年目で経験できるER症例
2019年度基幹型研修医 瀬堂川 拓
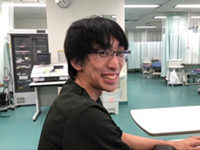
糸魚川総合病院は糸魚川市唯一の入院病床を持つ総合病院として、市内で発生する救急患者に対して可能な限り対応するという責務を負っております。現に当院の救急応需率は安定して90%程度を保持し続けており、「断らない救急」を少ない医療資源や医療者の下で可能な範囲で実現していると考えられます。
そんな当院の初期研修では、年間を通して週1日のER・総合外来研修が義務付けられており、初期研修医はERにやってくる救急患者のFirst touchをその重症度の如何にかかわらず行っていきます。そして、毎週金曜日には各ER症例についての検討会が行われ、症例について各専門科よりFeedbackを受けるシステムとなっております。
病院としては令和1年現在、年間を通してWalk in5205例、救急車1748例を引き受けている状況にあり、研修医は概ね600~1000例/人程度を年間に担当していることから、症例を奪いあうこともなく、十分な量的担保はされていると考えられます。
ここからはその内容について、平成24年度の基幹型研修医であられる松尾先生の症例(n=774)と令和1年度に私がERで経験した症例(n=1021)を用いてより具体的に提示したいと思います。
まず背景として8年前に松尾先生が初期研修をなさられていた当時に比べ、糸魚川地域では相当な高齢化が進んでおり令和2年4月現在、高齢化率は、37.1%にもなります。それに伴って当院の患者層も高齢化してきていますが、傷病者はほぼ全例が当院にいらっしゃる状況には変化がないため、乳児から超高齢者に至るまで幅広く診察ができる状況は維持されていることがわかります。(図1)
年齢別ER経験症例(図1)
また、来院する受診患者の重症度においても、いわゆる風邪から多発外傷、急性心筋梗塞、CPAなどに至るまで幅広くカバーしており、入院加療が必要な二次救急の割合はむしろ増加していることから、以前にもまして退院までのシームレスなフォローをしやすい環境となっていることがわかります。(図2)
救急対応別ER経験症例(図2)
そしてその多様性についても厚労省に定める「研修医が経験すべき症状」のほぼすべてを網羅できる環境(表1)であることに変わりはなく、患者それぞれの状態に合わせ、科を超えた対応を行っていくことができるようになる場所であるとわかります。(図3・表1)
科別ER経験症例(図3)
厚労省が定める経験すべき症状のER経験症例(表1)
| 症状 | 2011年 | 2019年 |
|---|---|---|
| 発熱 | 73 | 165 |
| 腹痛 | 73 | 74 |
| 頭痛 | 29 | 58 |
| 呼吸困難 | 38 | 36 |
| 食欲不振 | 7 | 34 |
| めまい | 27 | 33 |
| 嘔気・嘔吐 | 44 | 32 |
| 咳・痰 | 29 | 27 |
| 下痢・便秘 | 17 | 26 |
| 胸痛 | 24 | 22 |
| 関節痛 | 21 | 21 |
| 全身倦怠感 | 5 | 17 |
| 失神 | 11 | 16 |
| 発疹 | 25 | 14 |
| 動悸 | 13 | 13 |
| 腰痛 | 12 | 12 |
| 胸やけ | 2 | 12 |
| 四肢のしびれ | 1 | 9 |
| 歩行障害 | 2 | 7 |
| 尿量異常 | 4 | 7 |
| 鼻出血 | 3 | 5 |
| 排尿障害(尿失禁・排尿困難) | 3 | 5 |
| 痙攣発作 | 2 | 4 |
| 血尿 | 2 | 4 |
| 不安・抑うつ | 2 | 4 |
| 嗄声 | 0 | 3 |
| 視力障害・視野障害 | 4 | 2 |
| 結膜充血 | 5 | 2 |
| 黄疸 | 0 | 2 |
| 聴覚障害 | 0 | 2 |
| 浮腫 | 1 | 2 |
| 嚥下困難 | 1 | 1 |
| リンパ節腫脹 | 4 | 0 |
| 不眠 | 0 | 0 |
| 体重減少、体重増加 | 0 | 0 |
以上のように、当院の研修は質、量それぞれの側面から初期研修における多様な疾患に対する対応能力を育む上で適切な環境であることがわかります。また、ほぼすべての症例を当院でフォローし続けなければならないという地理的背景から他院ではまずもって不可能な「症例の前向き調査」を容易に行うことができるという特徴も兼ね備えており、疾患のその後のみならず、患者ひとりひとりを見つめ続けることができるのです。
日本はますます高齢化の一途をたどります。我々がこれまで調査、研究を続けて積み上げた医学的な根拠は役に立たなくなり、新たに「高齢者に対する」エビデンスを構築していくことが求められることもあるかと思います。そして、これからの医療者はそのような状況下でも常に患者第一に最善を追求していく必要があると思います。それが時に、命の灯が消えていくことを見守ることだとしても、です。その人の「ひととき」に目を背けることなく向かい合い続けなければならないのだと思います。私はこの1年のER実習を通して、当院ではだれ一人この心意気に欠けることなく、常に目の前の患者、社会と対峙し続けているのだと心から実感しました。
皆さんも我々と一緒に医師としての第一歩を踏み出しませんか。
